2023.08.10インボイス制度
インボイス対応の領収書の書き方|発行者・受領者それぞれの注意点について解説
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を適用するためのフォーマットが変わります。領収書やレシートの記載要件が変わるため、企業側での対応が必要です。本記事では、制度に対応した領収書の書き方や必要な対応などを解説します。
目次
● インボイス制度とは?
● 【見本】インボイス制度での請求書と領収書の違い
● インボイスに対応した領収書の書き方
● 領収書(簡易インボイス)の発行に必要な対応
● 領収書(簡易インボイス)を受け取る側の対応
● インボイス対応は無限の「らくらくパック」が解決!
● まとめ
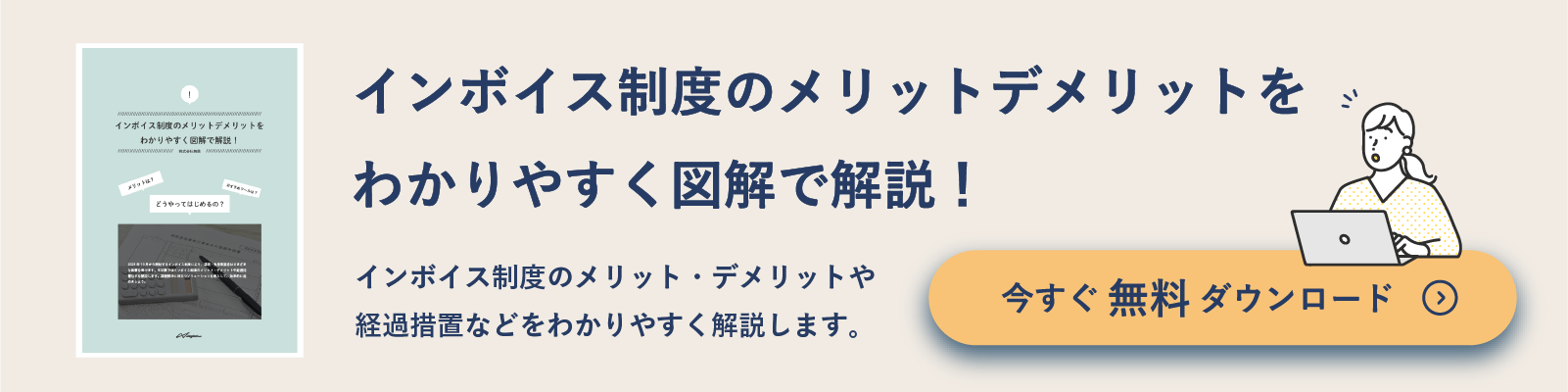
インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことです。仕入税額控除を受けるために必要な書類のことで、適格請求書の記載要件に対応した請求書や領収書などを指します。
制度開始については、2023年9月30日までは仕入税額控除を適用するために、区分記載請求書等保存方式に適合する書類が求められますが、同年10月1日から適格請求書等保存方式に移行します。
移行にあたり、区分記載請求書の記載要件に新しい記載項目が追加されます(記載項目の変更点など詳細は後述)。
インボイス制度が始まる背景には軽減税率の存在があります。現行の消費税には税率10%と軽減税率8%の2種類があるため、取引の適用税率や消費税額の正確な把握をするためにインボイス制度の導入がされることになりました。
インボイス制度の開始後の仕入税額控除の利用には適格請求書が必要ですが、条件さえ満たせば領収書やレシートも適格簡易請求書として認められます。それぞれの違いや条件については以下で解説します。
適格請求書とは、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額などを伝えるために発行する請求書や納品書などのことです。必要な情報を記載して作成する必要があります。
2023年10月1日からは、現在の区分記載請求書から新しい方式である適格請求書に変更する必要があります。
現行の記載要件に登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額を追加すれば、適格請求書として利用可能です。これら3項目を満たしていれば、電子記録や手書きでも問題ありません。
2023年10月のインボイス制度の開始に備え、記載事項を確認して対応しましょう。
適格請求書やインボイス制度についてのより詳しいことについては、以下の関連記事も併せてご覧ください。
(令和5年10月から始まるインボイス制度とは?図解を用いてわかりやすく解説!)
領収書やレシートは適格簡易請求書と呼ばれる、簡易版の適格請求書として扱われます。適格請求書の記載項目を簡略化したもので、特定の事業者が不特定多数と取引する場合に使用できるものです。
この適格簡易請求書を交付された場合でも仕入税額控除は受けられます。交付の際、その写しを保存する義務がある点も変わりません。
適格簡易請求書の記載事項は以下の通りです。ひとつでも記載漏れがあると無効になります。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率
(引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=6)
適格請求書との違いは、記載内容が簡素化されている点があります。具体的には、交付を受ける事業者の氏名・名称の記載が不要となり、税率ごとに分けた消費税額と適用税率の2点については、どちらか一方の記載でよいことになっています。
インボイスの発行事業者に該当し、不特定多数と取引する以下の事業を行っている場合は、適格簡易請求書を交付できます。
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
(引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=48)
①~⑤については不特定多数の制限がないため、業種に該当する場合はレシートなどの適格簡易請求書の発行が可能です。
適用事業者の条件などついては、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問25で回答されているため、詳しく知りたい場合は併せてご確認ください。
(国税庁|消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)
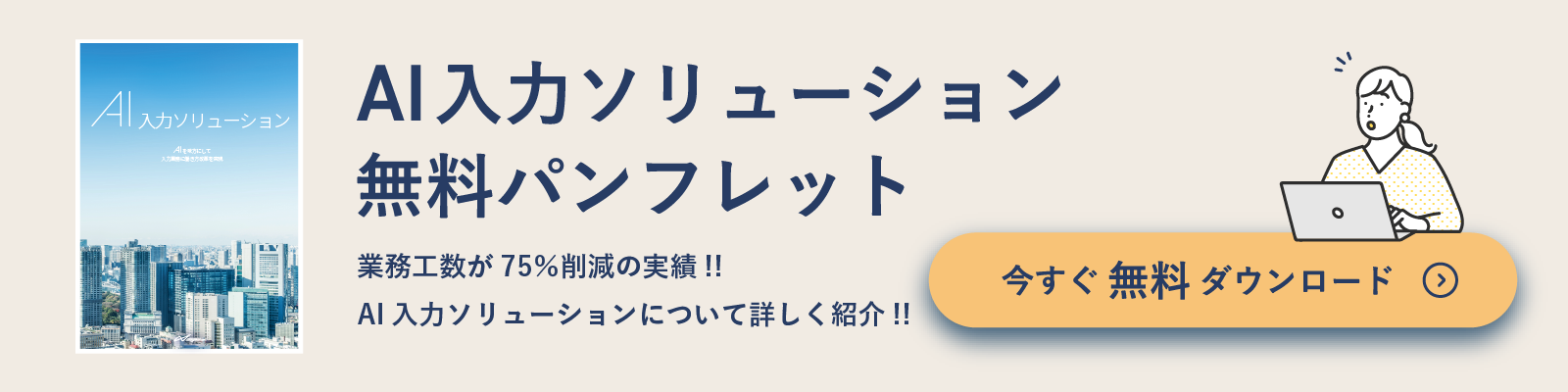
適格簡易請求書に該当する領収書やレシートの記載要件の書き方について解説します。
年月日の記載はインボイスの適用前から要件としてあります。領収書は金銭のやり取りがあった事実を裏付ける大切な証明書です。いつ取引をしたのか明確にするために書面上に取引日を記録しておきましょう。
取引日は、基本的に受領日を記入します。受領日とは、支払いや受け取りが行われた日付を指します。現金取引では、商品やサービスを利用して即座に支払った日付を記載します。
銀行振込の場合は、商品やサービスの利用日ではなく、実際の入金日を書きます。記載をミスした場合は、誤った領収書を回収し、再発行と記載したうえで新しいものを発行しましょう。
領収書の日付は年月日で記載しますが和暦や西暦は省略せずに記載しましょう。和暦は「令和」、西暦は「2020年」などです。和暦で初年度の場合は「元年」と書きます。
飲食店などでの接待や会食時は、当日ではなく後日に領収書を要求される場合があります。この場合、発行日ではなく支払日を記載します。支払日から一定期間が経過し、事実の確認が困難になった場合は発行を控える判断も重要です。
領収書には、発行者の氏名または名称、登録番号を記載します。個人事業主であれば屋号、法人なら企業名を書きましょう。支払者の氏名や会社名を正確に記載します。
登録番号とは、申請後に税務署から適格請求書発行事業者に与えられる番号です。法人番号がある場合は「T+法人番号」、法人番号がない場合は「T+13桁の固有番号」が登録番号となります。既存の領収書を使い回す場合は、企業名の下や目立つ場所に登録番号を追加しましょう。
業態などを踏まえ、小売業、飲食店、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業などのほか、これらの事業に準ずる事業で不特定多数を相手にする業種では領収書を受け取る側の氏名・名称を省略できます。
取引内容や金額を書面に記載します。レシートの場合は商品の詳細がありますが、領収書にはないため、取引した内容を書いておきましょう。書き方は、商品名やサービス名を含む具体的な情報をただし書きとして記載します。「お品代として」「お食事代として」などの表現でも記載できます。
重要なポイントとして、軽減税率対象の商品は一目で分かるようにしておきましょう。軽減税率の対象品目には「※」などの印をつけることで、軽減税率が適用された取引があったことを表せます。印を付ける場合はその意味の説明も記載しておきましょう。
取引の合計金額を税抜きまたは税込みで示します。このとき、8%と10%の軽減税率を別に分けて合計金額を記載する必要があります。
例えば、税率10%で2,000円の商品が2点、軽減税率8%で1,000円の商品が3点あったとしたら、次のように分けて記載します。
10%対象:4,000円
8%対象:3,000円
合計:7,000円
レシートの場合は、軽減税率の対象商品がある場合は個別に※や*などの印をつけると区別しやすいです。書き方を守らないと仕入税額控除の対象外になります。
領収書には税率ごとの消費税額を明記する必要があります。適格簡易請求書の場合は、税率と消費税額どちらか片方だけの記載でもよいです。例を挙げると以下のように記載できます。
・税率と消費税額を記載するパターン
10%対象:4,000円(うち消費税額400円)
8%対象:3,000円(うち消費税額240円)
・消費税額のみ記載するパターン
4,000円(うち消費税額400円)
3,000円(うち消費税額240円)
領収書を書く場合は正式名称で宛名を記載します。企業名については、(株)などの略称の使用はできません。個人名の場合は上様ではなく、氏名を記入します。分からない場合は相手に尋ねるか、直接書いてもらうようにしましょう。なお、宛名は小売業など不特定多数の相手に発行するレシートでは記載不要です。
領収書を発行する場合に準備が必要なことについて解説します。
制度開始の2023年10月1日から領収書を適格請求書として発行するためには、事業者は適格請求書発行事業者として登録する必要があります。制度開始当日に登録を間に合わせるには、2023年9月30日までに税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。まだ申請していない場合は、早めに申請しましょう。
申請が承認されると、登録番号などの通知が届き、国税庁の公式サイトで公表されます。適格請求書発行事業者となったら、必要な項目を含んだインボイスを発行し、その写しを適切に保存することが求められます。取引のある売上先に登録事業者であることを伝えましょう。
免税事業者は、制度開始後でも登録希望日から登録を受けたことにできます。ただし、申請書類を提出した日から15日以降の日付です。登録完了が希望日以降だった場合でも希望日を登録日にできます。
インボイスの対応には領収書のフォーマット整備が必要です。新たに必要となる項目は「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」です。3万円未満の取引でも領収書などを発行しないと仕入税額控除が適用されないため注意してください。
制度開始日である2023年10月1日までにフォーマットを準備しておくことが重要です。
また、インボイスを効率的に発行するためにも、専用フォーマット対応の領収書を作成・保存できる専用ツールを活用することをおすすめします。ツールの活用はミスの防止や書き間違いなどのトラブルの減少にもなります。
なお、制度開始前に登録番号を取得できている場合は、区分記載請求書に登録番号を記載しても問題ありません。
領収書の保管期間は7年間です。保管期間内に領収書を紛失すると税務調査で追徴課税が課せられることがあるため、気をつけましょう。
適格請求書発行事業者は、適格請求書の代わりに電子記録を提供できます。電子記録の内容は、適格請求書と同じ内容が記載されている必要があります。保管方法は、紙の領収書だった場合は紙で、電子で受け取った場合は電子データのままで保管します。
2023年末までは電子インボイスの紙保管が認められていましたが、2024年1月からは電子インボイスの電子保存が義務付けられます。
電子で保存する場合は、電子帳簿等保存法の要件を満たすことが求められます。要件として、改ざん防止措置や提示しやすいように検索機能を確保すること、取引年月日などの検索条件を設定できることなどが定められています。
2023年9月30日までは、3万円未満の取引で領収書やレシートを保存していなくても仕入税額控除が適用されます。しかし、制度開始後は金額を問わず発行しなくてはなりません。領収書がない場合は仕入税額控除の対象外です。
ただし、発行が難しい下記のようなケースでは、売り手側の交付義務が免除されます。買い手側は仕入税額控除のために帳簿の保存が必要です。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者
が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限
ります。)
(引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=23)
さらに、負担軽減措置として、一定期間の課税売上高が1億円以下または課税売上高が5千万円以下の事業者は、1万円未満の取引での課税仕入れであれば、帳簿のみの保存で控除ができます。対象期間は2023年10月1日から2029年9月30日までです。
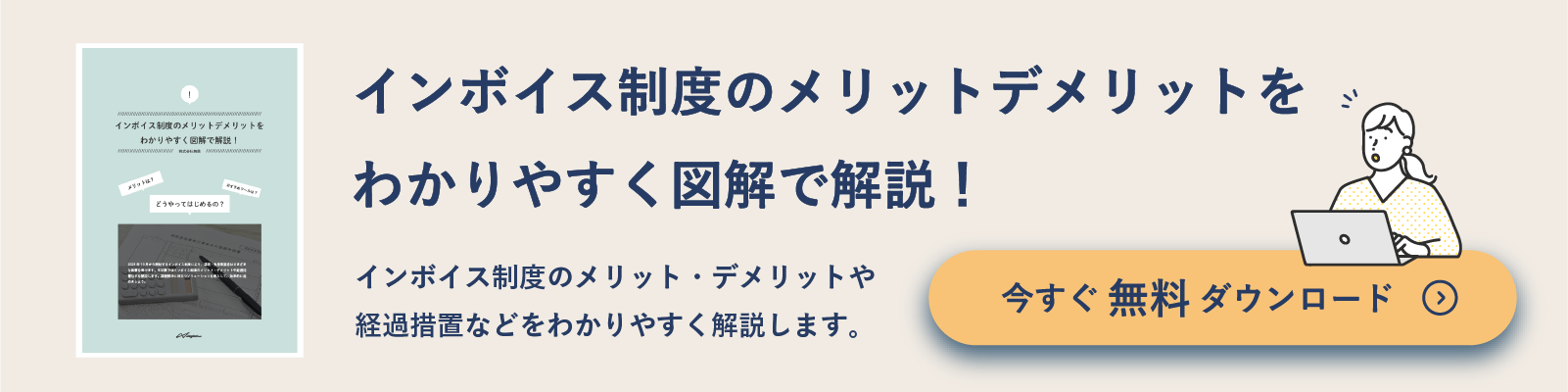
受け取る側でやっておくべき対応について解説します。仕分けや保管方法に注意しましょう。
制度開始後は受け取った領収書の仕分けに注意が必要です。適格請求書と適格簡易請求書を受け取った取引のみ仕入税額控除できるため、該当する領収書とそれ以外を分ける必要があります。また、取引時は相手が登録番号のある適格請求書発行事業者かどうかも確認しましょう。
領収書を仕分け・確認する際は、取引日時点で登録番号を受けている事業者か、記載要件を満たしているかどうかを確認します。必要事項の不備があった場合、受け取り側で勝手に補完できないため、発行側に再発行を依頼する必要があります。
免税事業者との取引で受け取った登録番号がない領収書の場合は、別途仕分けを行い、経過措置の適用を行うことで控除対象になります。登録番号なしの領収書は別に分けて保存しておきましょう。
また、領収書を手作業ですべて分類するのは手間の観点から現実的ではないため、自社に合ったソリューションを導入しておくことをおすすめします。
発行者と同じく、受け取った側も領収書を原則7年間保管しておく必要があります。ただし、法人で赤字が発生した事業年度の場合は最大10年間保存となります。
電子データで領収書を受け取る場合、2024年1月1日以降は電子帳簿保存法に基づいて電子データのままで保存する必要があります。
電子帳簿保存法に基づき、レシートや領収書のスキャンや写真データの保存が可能で、原本の保管は不要です。また、会計システムを活用してデータを保存することもできます。
取引によって紙や電子メール、システムなどの様々な形式で領収書を受領することが想定されるため、手作業ではなくインボイスの処理を自動化できる仕組みを整備しておくことも重要です。
受領したインボイスが必要事項を含んでいるか確認しましょう。仕入税額控除を適用するには、記載要件を満たした領収書である必要があります。記載事項の登録番号・内容・消費税区分が適切に記載されているか確認しましょう。
誤りを防ぐためにも大切なステップです。確認の結果、不備があることが分かった場合は、受け取った側で勝手に修正できないため、発行側に修正した正しい領収書の交付を依頼する必要があります。
インボイスの対応でお困りなら、無限の「らくらくパック」で簡単に解決できます。らくらくパックは、DX推進や制度利用に必要な電子帳簿保存法、適格請求書の要件、テレワーク環境へ対応したワークフロー・ソリューションを提供します。ユーザーフレンドリーな操作性のため、IT慣れしていない人でも使いやすく、現場で安心して利用しやすいです。
AI入力ソリューションを利用して、入力業務を自動化し効率化することも可能です。AI OCR機能によって、紙書類を高精度にデータ化できます。PDFやExcel、Wordなどのファイル形式にも対応しており、申請などに使用可能です。そのほかにもデータ連携、メール送信など多彩な機能を利用できます。
導入後のサポートも万全で、専任の担当者がアフターフォローを行います。専任コンサルタントによるDXサポートや適切な提案も受けられ、円滑な企業のDX実現をサポートします。ぜひご検討ください。
らくらくパックの詳細については、こちらでも紹介しています。ぜひご覧ください。
(電子帳簿保存法・インボイス制度対応『らくらくパック』)
インボイス制度の開始後は、適格請求書の記載要件に一致するフォーマットで帳票を作成しないと、仕入税額控除を適用できなくなります。領収書、レシートも適格簡易請求書として認められており、控除の適用に利用可能です。
また、インボイスの発行側と受領側に帳票の処理や保管をする仕組みの準備が求められます。対応が遅れると控除の面で不利になるため、早い段階でインボイス制度関連のソリューションを導入し、対応を済ませておくとよいでしょう。
株式会社無限やソリューションなどへの資料請求・お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。